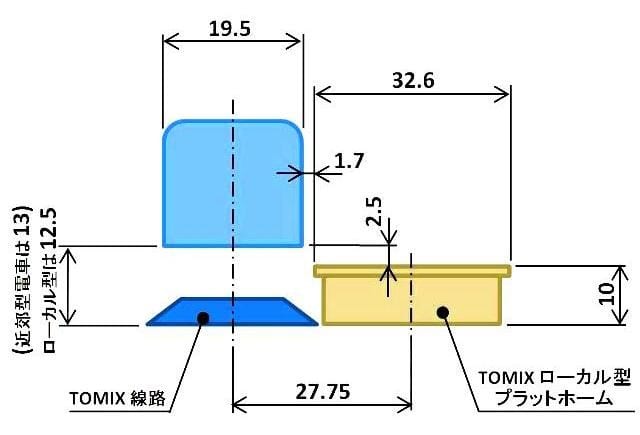静岡ホビーショー2018 のレポート。 続編です。
こちらは SANKEI のブースです。
ペーパー製の みにちゅあーと。 ジブリ作品を得意としていますが、Zゲージ、Nゲージ、HOゲージ用の 昭和な建物も多く手掛けています。
![]()
半透明の材料でカーテンや障子を入れて、内部照明を仕込むと楽しめそうです。 窓越しに人物が見えるのも良いのでは。
![]()
KATO のブースです。 スマートコントローラー が目を引きます。
DD51 の サウンドカード を実演していました。 貨車の連結音 がリアルに再現されていました。
![]()
近日発売の 瀬戸/あさかぜ や ガールズパンツァー、HOゲージの キハ110 などが展示してありました。
![]()
KATO のブースの中に NOCH ( ノッホ ) の特設コーナーがありました。
鉄道模型ジオラマ先進国のヨーロッパから来て、模型作りの楽しさを母国語で語ってくれました。
![]()
PLATZ ( プラッツ ) のブースです。
地面に木工用ボンドを塗っておき、電極をつないだ 黒い棒状のものでパウダーを撒きます。 すると、繊維が立った状態で草地を表現できます。 実演を見せて頂きました。
![]()
地面作りに必要なパウダー類です。 パッケージには PLATZ と書いてありますが、NOCH の製品です。 KATO と同様、代理店契約を結んでいるのでしょう。
![]()
PLATZ は鉄道模型に限らず、多様なホビー商品を扱っています。
PICO 製品はその昔、9mmナロー フレキシブルレール や 25°クロスレール を購入した事があります。 需要がなくなることは 無いと思っています。
![]()
GREENMAX のブースです。
西武線、東武線、東急線、京王線 など、新製品が予定されています。
![]()
他社の車両に 動力ユニット を組み込める構造になっているのが GREENMAX の売りでもあります。
![]()
MICRO ACE のブースです。
スピーカーシステム の紹介です。 Bluetooth対応スピーカー が車両に載って、スマホなどからサウンドの操作をします。
他社のサウンドシステムは 用意された音源の中からサウンドを選択しますが、こちらは無限に選べます。
また、固定のスピーカーからの音ではなく、レイアウトを移動する車両から音が出るので、臨場感があります。
![]()
東武鉄道の SL大樹編成 が夏に発売予定です。
![]()
その他、MICROACE らしいラインナップが 市場を賑わせそうです。
![]()
今回の展示会で強く感じたのは、鉄道模型業界は サウンド対決という新たな局面に突き当たったということ。 熾烈な戦いになる予感です。
IT企業との事業提携は必須と思われます。。。
こちらは SANKEI のブースです。
ペーパー製の みにちゅあーと。 ジブリ作品を得意としていますが、Zゲージ、Nゲージ、HOゲージ用の 昭和な建物も多く手掛けています。

半透明の材料でカーテンや障子を入れて、内部照明を仕込むと楽しめそうです。 窓越しに人物が見えるのも良いのでは。

KATO のブースです。 スマートコントローラー が目を引きます。
DD51 の サウンドカード を実演していました。 貨車の連結音 がリアルに再現されていました。

近日発売の 瀬戸/あさかぜ や ガールズパンツァー、HOゲージの キハ110 などが展示してありました。

KATO のブースの中に NOCH ( ノッホ ) の特設コーナーがありました。
鉄道模型ジオラマ先進国のヨーロッパから来て、模型作りの楽しさを母国語で語ってくれました。

PLATZ ( プラッツ ) のブースです。
地面に木工用ボンドを塗っておき、電極をつないだ 黒い棒状のものでパウダーを撒きます。 すると、繊維が立った状態で草地を表現できます。 実演を見せて頂きました。

地面作りに必要なパウダー類です。 パッケージには PLATZ と書いてありますが、NOCH の製品です。 KATO と同様、代理店契約を結んでいるのでしょう。

PLATZ は鉄道模型に限らず、多様なホビー商品を扱っています。
PICO 製品はその昔、9mmナロー フレキシブルレール や 25°クロスレール を購入した事があります。 需要がなくなることは 無いと思っています。

GREENMAX のブースです。
西武線、東武線、東急線、京王線 など、新製品が予定されています。

他社の車両に 動力ユニット を組み込める構造になっているのが GREENMAX の売りでもあります。

MICRO ACE のブースです。
スピーカーシステム の紹介です。 Bluetooth対応スピーカー が車両に載って、スマホなどからサウンドの操作をします。
他社のサウンドシステムは 用意された音源の中からサウンドを選択しますが、こちらは無限に選べます。
また、固定のスピーカーからの音ではなく、レイアウトを移動する車両から音が出るので、臨場感があります。

東武鉄道の SL大樹編成 が夏に発売予定です。

その他、MICROACE らしいラインナップが 市場を賑わせそうです。

今回の展示会で強く感じたのは、鉄道模型業界は サウンド対決という新たな局面に突き当たったということ。 熾烈な戦いになる予感です。
IT企業との事業提携は必須と思われます。。。













 』 奥が深いです。
』 奥が深いです。